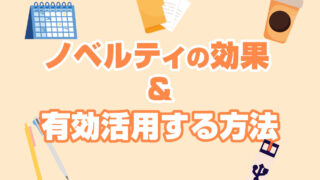自分達の商品やサービスを届けるために必要不可欠といっても過言でないことがあります。
プロモーション活動です。
せっかく良い商品をつくったとしても、プロモーションを実施しなかったために、その商品を欲している顧客へ届けられていない可能性(≒機会損失)があります。
本当にモッタイナイことです。
大企業のように専門の部署があればいいのですが、中小企業の場合、そこまでの余裕はない。
当社もそんな余裕はありません。
とはいえ、プロモーション活動を推進しなければならない。
だからこそ自分達にあったプロモーション方法を選ぶことが重要です。
そこで今回はプロモーションにはどのような種類があるのか、それぞれのメリット・デメリットを紹介していきます。
\見ないと損かも?/
プロモーション活動の柱:製品、価格、流通、販促
「プロモーション活動」は以下の4要素から構成されています。
- 製品(product):どのような商品やサービスを提供するか
- 価格(price):商品やサービスの価格
- 流通(place):流通させるルートや販売場所
- 販促(promotion):広告宣伝・販売促進など
上記の製品、価格、流通に自社のサービスや商品を当てはめることで、販促がみえてきます。
顧客への認知を高め購買行動を促進させるために、重要なことですので、試してみる価値ありです。
当社の場合
- 製品(product):環境に優しいグッズ
- 価格(price):1,000円未満
- 流通(place):ホームページ経由、既存のお客様からの口コミなど
- 販促(promotion):ブログ記事更新、リスティング広告、パンフレット配布
といった具合でプロモーション活動を設定しています。
どれも購買してもらうために大事ですが、今回は販促(Promotion)について紹介していきます。
広告(有料)
テレビ・ラジオ広告(CM):
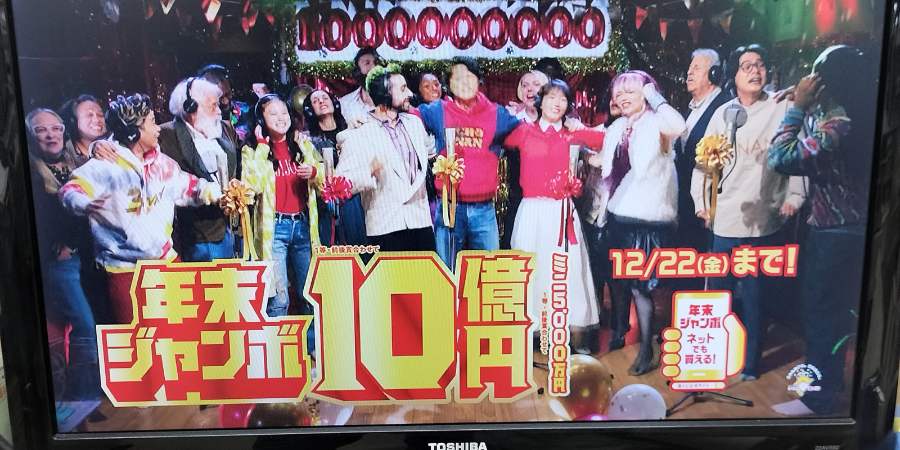
大人数にアプローチ可能な手法です。
ブランド認知度を高める手段として有効で、主に大手企業が活用しています。
- メリット: アプローチ可能な人数がかなり多い
- デメリット: 制作・放送費用が高く、効果測定が難しい
雑誌広告:

雑誌の内容に合わせた広告を発行できるため、ターゲットを絞ることができます。
- メリット: ターゲット層が明確で、それに合わせたがアプローチが可能
- デメリット: 発行スケジュールに合わせた計画が必要で、コストが掛かりやすい
新聞広告:

地域性や即時性など重要な情報を伝える媒体として活用されています。
- メリット: 中高年へのアプローチに適している
- デメリット: 若年層へのアプローチが難しい
交通広告:

電車やバスの車内、駅の構内などのスペースを活用して展開されている広告です。
移動中の人々に直接訴えかけることができます。
- メリット: 移動中の人の目を引くことが可能、ターゲットに何度も訴求できる
※通学・通勤で利用する人に対して何度もアプローチすることができます。 - デメリット: 広告の差別化が難しい
※同じサイズの広告スペースに他社の広告も並んで掲載されているため、デザインによっては目立たなくなる可能性があります。
リスティング広告:

主にGoogleやYahoo!を検索した時に表示される広告です。クリックごとに費用が発生します。
- メリット: 購買意欲があるユーザーにアプローチできる、配信開始や停止をスピーディーに行える
- デメリット: 認知(潜在層)向きではない
※検索自体は目的をもって行動する人向けですので、今まで商品やサービスを知らなかった人に対する認知拡大には向いていません。
当社も出稿したことがあり、そこでお問合せをいただいたお客様と今でもお取引があります。
自社の商品を検索している顧客がどのようなキーワードで検索しているのか、文章はどうするのか等勉強すべき内容は多いですが、きちんと広告運用できれば、費用以上の成果を出すことは可能です。
SNS広告(YouTubeやTwitterなど):

ターゲットの興味や嗜好に基づき、ソーシャルメディア上で広告を展開。シェアやコメントを通じて拡散されやすい特徴をもちます。
- メリット: 情報拡散力で認知拡大を狙える、ユーザーと手軽にコミュニケーションをとれる
- デメリット: 高年齢層へのアプローチが困難、炎上するリスクがある
ポスティング:

直接手渡しやポスト投函することで、ターゲットに直接するアプローチ方法です。
- メリット: 配布エリアを細かく指定できる、リーチできる年齢層が広い
※インターネットを利用しない層(高齢者)へアプローチできます。 - デメリット: クレームが発生する可能性がある
チラシを不要とする方から直接クレームを受けるかもしれません。
パブリシティ:広報活動(無料)
広告は有料で情報掲載しますが、パブリシティは基本的に無償で情報を届けます。
プレスリリース:

企業の重要な出来事や情報を報道機関に提供。信頼性の高い情報発信が期待されます。
- メリット: 信頼性が高まり報道機関を通じて多くの人に情報が届く、費用を抑えられる
- デメリット: 確実に記事化されるわけではない、記者側に編集権があるため内容のコントロールは困難
当社でもプレスリリースを報道関係者の方々へ連絡し、掲載していただいたことがあります。
掲載していただき即売上UPというわけではありませんが、商品の信頼性向上に一役買ってくれています。
ホームページ更新:

最新の情報やコンテンツを随時更新することで顧客満足度向上に貢献します。
- メリット: 自分達が所有している発信媒体であるため、コントロールしやすい
- デメリット: 定期的な更新が必要、専門知識が求められる
※専門知識を有していれば、お金を掛けずに(レンタルサーバー代:1,000円/月程度)情報発信できます。
文章や画像を作成する分手間は掛かりますが、一度コンテンツを作成してしまえば、自動的に集客してくれますので、とても便利です。
SNSの運用:
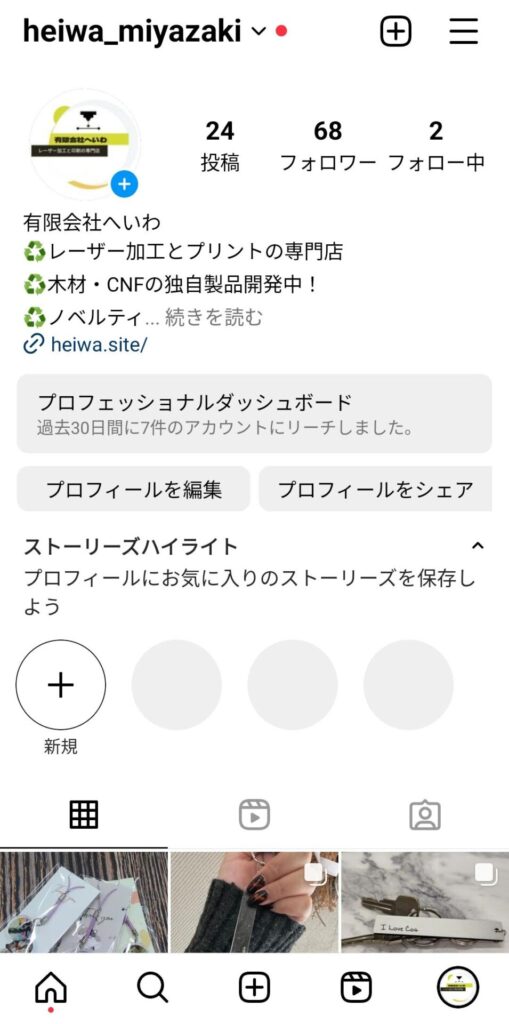
ソーシャルメディア上で企業や製品の魅力を発信します。手軽に始めやすい点も魅力的です。
- メリット: ユーザーとの対話が可能で、拡散が期待できる
- デメリット: ネガティブな意見も拡散される可能性があり、コンテンツ作成が手間がかかる
最近ではGoogle検索を活用せずにInstagramやTwitterからのみ情報を収集する層も出てきておりますので、顧客の取りこぼしを防ぐためにも試す価値はあります。
セールスプロモーション(販促)
サンプル品の配布:

ブランドのサンプル品を配布することで、認知度拡大を狙います。
- メリット: 実際に使ってもらうことで効果を実感してもらいやすい、顧客の反応がわかる
- デメリット: 配布するための場所やスタッフが必要
ノベルティの配布

会社名やブランド名をターゲットが欲している製品に印字して配布します。
- メリット: 認知度を高めることができる、一瞬目にするだけの広告と異なり、そのノベルティを使うたびに思い出してもらうことも可能
- デメリット: ターゲットに合ったノベルティを選ばないと効果的でない
詳しく知りたい場合はこちらをご覧ください。
期間限定のセール、特典付与:

期間限定や特典の魅力を利用して売上を促進します。
- メリット: 購買意欲を促進し、短期的な売上向上が期待できる
- デメリット: 利益率が低下しやすい
店頭プロモーション(ディスプレイの工夫やPOPの掲載、デモンストレーション販売):

販売場所での直接的にアプローチすることで、商品の特徴を顧客にリアルに伝えます。
- メリット: 商品のリアルな魅力を伝えやすい、商品・サービスにある程度興味関心を持った見込み顧客に直接アプローチできる
- デメリット: 施策の規模や効果は来店者数の制約を受ける
展示会やイベントの開催、ブース出展:

東京ビックサイトや幕張メッセといった施設で開催される展示会にて自社のブースを出展します。
- メリット: イベントのテーマに合わせて出展できるためターゲットを絞れる、顧客とダイレクトに接触できるため反応を確認しやすい
- デメリット: 費用と労力がかかる
※遠方の場合、人数や期間にもよりますが最低でも数十万は必要です。(交通費・人件費・出店費用など)
セミナー開催:

自社の専門性に関心のある顧客を集客してセミナーを開催します。
- メリット: 専門的な知識や情報提供を通じて顧客の関心を引き、信頼度を向上させる。
- デメリット: 参加者の獲得が難しく、適切な情報提供が必要。
ポイントカードやクーポン:

特典を活用したリピーターを生み出す定番の仕組みです。
- メリット: 購買意欲を促進させリピーター獲得に繋げる、購買回数の増加を期待できる
- デメリット: 利益率の低下
メルマガ配信:

顧客とのダイレクトなコミュニケーションを通じて、新着情報や特典を提供し顧客とのつながりを保ちます。
- メリット: 直接的な情報提供、リピーターの獲得、SNSなどと違いプラットフォームに左右されない
- デメリット: 購読者の減少やスパム扱いのリスクがある。
代理(販売)店活用:

代理店にパンフレットを配布してもらう方法もあります。
- メリット:営業や顧客管理をお任せできる
- デメリット:代理店の手数料が発生するため利益率が下がる
大事なことはPDCAを何度も繰り返す
どのプロモーション方法が自社にとって適切なのかは、実際に試してみることで徐々にみえてきます。
最初から成果を出せるといいのですが、そう簡単ではありません。
私たちもSNS発信やリスティング広告など様々な方法を試しました。
その際に意識したことがPDCAの高速回転です。
PDCAに沿ってプロモーションを試し続ける
これを何度も繰り返すことで、適切なプロモーション方法を理解し、お問合せ件数を増やすことができました。